今回は、個人が貰う株式からの配当金の所得税・住民税の区分・申告方法(配当控除も含めて)についてまとめていきます。
株式の配当金にかかる所得税・住民税の申告方法はかなり複雑になります。
少しでも所得税・住民税の納税額を減らしたい人は、以下で解説する3通りの申告方法を理解してください。
個人所有の株式の課税関係について
株式から利益を得る方法は、以下の2種類に分けられます。
- 株式を保有して配当金を得ること(インカムゲインといいます)
- 株式を売却して売却益を得ること(キャピタルゲインといいます)
個人が、❶の場合に得た配当金は配当所得に分類され、❷の場合に得た売却益は譲渡所得に分類されます。
配当所得・譲渡所得の計算方法はそれぞれ異なりますが、いずれも所得税・住民税の課税対象になります。
配当所得の申告方法について
配当所得の申告方法について、以下の3種類が用意されています。
- 申告不要制度
- 総合課税制度
- 申告分離制度
申告不要制度
申告不要制度は、所得税・住民税の確定申告を行わず、配当金の受取時に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収が行われるだけで納税を完了する方法です(源泉分離課税制度とも呼ばれます)。
自分で確定申告をする手間を省けるため一番利用しやすい制度です。
なお、源泉徴収とは、証券会社が配当金を支払う際に、所得税分・住民税税分を事前に差し引き、国等に納付する制度です。
申告不要制度を利用したい場合、証券会社の口座を特定口座(源泉徴収あり)に設定しよう!
総合課税制度
総合課税制度とは、受け取った配当金を他の所得(事業所得・給与所得・不動産所得等)と合算して、所得税・住民税を計算し、納税者が申告をする方法です。
総合課税制度を選択すると、課税される所得金額によって、所得税率は5%~45%と変化し、住民税率は10%になります。
申告不要制度や申告分離課税制度の場合の税率が20.315%(所得税15.315%、住民税5%)なので、課税される所得金額が少なければ、総合課税制度を選択した方が有利になり、課税される所得金額が多くなれば、総合課税を選択した方が不利になります。
なお、総合課税制度の場合のみ、配当控除が適用されることになります(配当控除については下で説明します)。
また、以下の配当金がある場合は、必ず総合課税制度を適用して確定申告を行わなければなりません。
- 非上場会社株式からの配当金(10万円超)
- 大口株主(3%以上の株式を保有する株主)になっている上場会社株式からの配当金
ちなみに、非上場会社株式からの配当金や大口株主になっている上場会社株式からの配当金に対しては、源泉徴収(所得税20.42%)が行われています。
ただし、所得税だけで20.42%が源泉徴収されており、住民税の源泉徴収はされていません。
住民税の確定申告をする際には、源泉徴収がされていない点に注意する必要があります。
申告分離課税制度
申告分離課税制度とは、受け取った配当金を他の所得(事業所得・給与所得・不動産所得等)と合算しないで、分離して税額を計算し、納税者が確定申告を行い、納税をする方法です。
申告分離課税制度を適用した場合、上場会社株式の譲渡損失と上場会社株式の配当金を損益通算できます。
ただし、非上場会社株式の配当金は損益通算できませんので注意が必要です!
損益通算とは、例えば、上場株式A社の株式を売却して、40万円の赤字があり、上場会社B社より100万円の配当金を貰っていた場合、100万円-40万=60万円に対してだけ所得税が課税される方法です。
なお、申告分離課税制度を適用した時に適用される税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)になります。
よって、前述の例えだと、60万円×20.315%≒12.19万円が所得税・住民税の納税額になります。
申告分離課税のメリットは、上場会社株式の譲渡損があるときに、上場会社株式の配当所得を減額し、所得税の納税額を減らしてくれることです。
配当控除とは
配当控除とは、国内株式の配当金について、総合課税制度を適用して所得税・住民税の確定申告をした場合に、適用される税額控除のことです。
個人の株主が会社から貰う配当金は、法人税が支払われた後の利益を原資とする配当になります。
よって、個人の株主が配当金を貰った時にさらに所得税や住民税を掛けてしまうと、法人税と所得税・住民税の二重課税が生じてしまいます。
そこで、法人税と所得税・住民税の二重課税を避けるために、税額控除という形で所得税・住民税の支払額を減額させる制度が配当控除になります。
配当控除の控除率
配当控除は、課税総所得金額等が1,000万円以下か1,000万円超かで控除率が異なります。
課税総所得金額等が1,000万以下の場合、所得税については、配当所得の金額の10%が控除されます。
課税総所得金額等が1,000万円を超える場合は、1,000万円を超えた部分について、所得税の控除率は、配当所得の金額の5%になります。
なお、住民税については、配当所得の金額の2.8%が控除されることになります。
課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税長期(短期)譲渡所得の金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額および先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。大雑把に言ってしまうと、事業所得や給与所得などの合計額ことです!
まとめ
非上場会社の株式からの配当金(10万円超)や大口の株主の配当金の場合には、総合課税制度のみしか適用できません(選択の余地はない!)。
それ以外の株式の配当金の場合、申告不要制度を利用するのが、所得税や住民税の計算を自動的にしてもらえて、さらに確定申告もしなくて良いので、一番簡単でストレスがありません。
ただし、少しでも税金を減らしたい人は、総合課税制度や申告分離課税制度を検討してみて下さい。

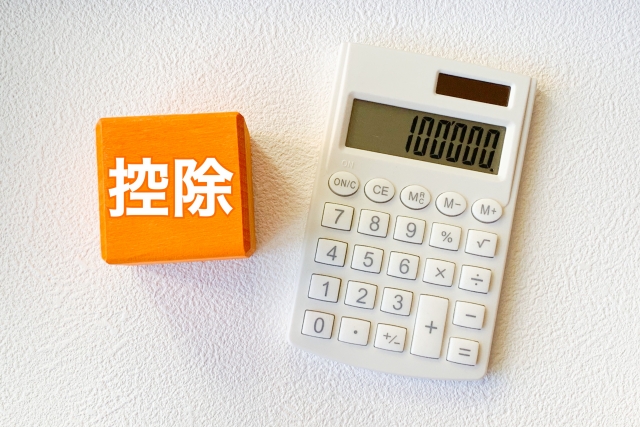
コメント