マイホームを取得したり、増築したりする場合に、銀行融資を受けると、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を利用できます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、所得税法上、税額控除と呼ばれるもので、最終的な所得税の納付額から直接一定額を控除できる制度です。
この住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、税制改正で制度の継ぎ足しが頻繁に行われている関係で、非常に難解な制度になっています。
ただし、理論的には、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の基本となる考え方は一つです。
今回は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の基本について確認していきましょう。
特定居住用財産の買換え特例や3000万円の特別控除との関係について
マイホームの購入・売却に係る税額控除には、特定居住用財産の買換え特例やマイホームの売却時の3,000万円の特別控除があります。
これらが適用された場合には、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は適用できません。
特に、マイホームの売却時の3,000万円の特別控除は、要件を満たすためのハードルが低く、非常に使いやすい制度です。
よって、古いマイホームを売却して、新しいマイホームを購入する場合などは、マイホームの売却時の3,000万円の特別控除を適用するか、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を適用するか判断が必要になります。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、正式名称を住宅借入金等特別控除といい、個人が住宅ローンを利用した際に、所得税の税額控除が受けられる制度です。
なお、所得税から控除しきれない住宅ローン控除の金額は、翌年度の住民税からも税金が控除されます。
住宅ローン控除は、新築住宅の購入以外にも、中古住宅の購入やリフォームでも利用できます。
なお、昨今の住宅ローン控除の改正では、環境配慮型の住宅に対して、住宅ローン控除を利用させようという改正が多いです。
住宅ローン控除は、中古住宅の購入やリフォームでも利用できることを覚えておこう!
住宅ローン控除の控除率・控除期間
新築住宅の場合、控除率は0.7%で控除期間は13年間になります。
既存住宅やリフォームの場合、控除率は0.7%で控除期間は10年になります。
例えば、新築住宅で住宅ローンを銀行より4,000万円借りて、年末借入金残高が3,000万円の場合、3,000万円×0.7%=21万円/年の税額控除が受けられます。
なお、新築住宅や中古住宅がどれだけ環境に配慮した住宅かで、住宅ローンの残高のうちどれだけ住宅ローン控除の対象金額になるかが決まります。
例えば、省エネ基準適合住宅を新築した場合、住宅ローン控除の対象になる金額は3,000万円までです。
仮に年末借入金残高が5,000万円あったとしても、3,000万円×0.7%=21万円までしか住宅ローン控除は認められません。
共働きの世帯で借入金残高が多額になる場合は、ペアローンを使い、住宅ローン控除を夫と妻で2重で適用する方法があります。住宅ローン控除を2重で適用することで節税できる所得税・住民税を考えると検討する価値はあるでしょう!
住宅ローン控除の要件
住宅ローン控除を受けるためには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。
- 借入金要件
- 取得住宅等の要件
- 本人の所得要件
借入金要件
住宅ローン控除の対象になる借り入れは、完済まで10年以上の分割返済になっている借入金であることが要件になっています。
住宅ローンを借り換える場合、新しい住宅ローンの完済までの期間が10年を切っている金銭消費貸借契約を銀行としてしまうと住宅ローン控除がその時点から適用できなくなるので注意しましょう!
取得住宅等の要件
マイホームを取得した日から6か月以内に床面積の2分の1以上を居住の用に供することが必要になります。
また、床面積は40㎡以上で、中古住宅の場合、築20年以内であることが要件になります。
床面積の要件は50㎡→40㎡に変更になり、かなり多くの物件で住宅ローン控除を適用できるようになりました!
本人の所得要件
本人の合計所得金額(事業や会社員としての儲けの合計)が3,000万円以下であることが要件になります。
ただし、マイホームの床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、本人の合計所得金額が1,000万円以下までと要件が厳しくなります。
合計所得金額とは、給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得(公的年金等の所得)などの合計額のことです。なお、所得とはもうけのことで、稼いだ金額(収入)から必要経費などを引いた金額のことです。
確定申告について
住宅ローン控除を適用するためには、確定申告をすることが必要になります。
ただし、1年目にきちんと確定申告をした会社員で、2年目以降も住宅ローン控除を受ける場合、会社が行う年末調整で手続きが完了することになります。
よって、2年目以降は、税務署から送付されてくる「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を会社に提出することで住宅ローン控除の適用を受けることができます。
会社員かそれ以外かで2年目以降の住宅ローン控除を適用するための手続きが異なるので注意が必要です!

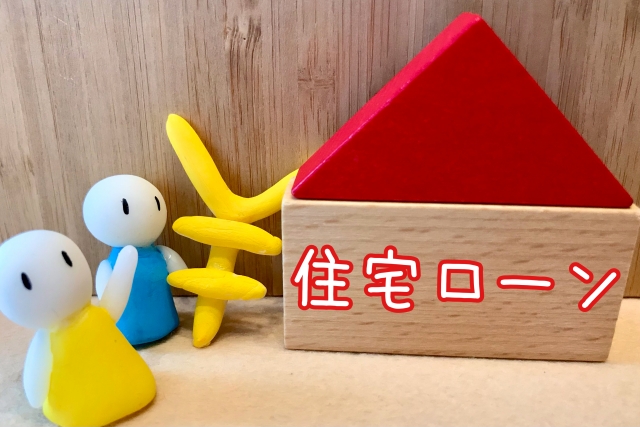
コメント