国民皆保険の元、日本国民であるならば誰もが加入している公的医療保険(健康保険)ですが、実は中身について知っているか知らないかでライフプランニングに大きな影響が出てきます。
例えば、将来のケガや病気に備えて民間の保険に加入する際に、公的医療保険の内容を知らないと保険会社の提案のままに加入してしまい、実は過剰な保険契約であったということもよくあります。
今回は、公的医療保険(健康保険)の基礎的な内容を確認していきましょう。
公的医療保険の運営母体は4つある!
公的医療保険は国民全員からお金を集めて、仮にあなたが病院にお世話になった場合に、医療費の7割を負担してくれる制度です。
この制度のお陰で、3割の自己負担額で病院のお世話になることができます。
公的医療保険ですが、主な運営母体が4つあります。
中小企業の従業員が加入する協会けんぽ、大企業の従業員が加入する組合健保、自営業者や年金受給者が加入する国保、75歳になると協会けんぽ、組合健保、国保から脱退して自動的に加入させられる後期高齢者医療制度の4つです。
協会けんぽ(協会管掌健康保険)について
協会けんぽは、全国健康保険協会が運営する中小企業の従業員のための健康保険です。
協会けんぽの場合、従業員と会社の保険料の負担割合は折半になります。
協会けんぽは、従業員のための健康保険ですが、2か月以上継続して働いていた従業員ならば、退職後も本人が希望すれば2年間加入を継続できる任意継続という制度があります。
なお、任意継続の場合の保険料は、全額自己負担になり、退職日の翌日から20日以内に任意継続の申請をする必要があります。
協会けんぽの保険内容の主なものは以下の通りになります。
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
従業員が療養のために、連続する3日間を含む4日以上仕事を休む場合に、最長で1年6か月間は傷病手当金を貰うことができます。
傷病手当金の金額は、標準報酬月額の平均を30日で割った金額の3分の2に相当する金額になります。
高額療養費(こうがくりょうようひ)
高額療養費とは、月にかかった医療費の自己負担額(全体の3割)が高額になった場合に、自己負担限度額(8万円強の人が多い)を超えた分の金額が、後から払い戻される制度です。
出産一時金
従業員が出産した場合には、出産育児一時金、従業員の家族が出産した場合には家族出産育児一時金が支給されます。
支給額は一人につき50万円となります。
出産手当金
出産日前42日と出産日後56日の間、休職した期間に応じて従業員に支給されるのが出産手当金です。
支給金額は、標準報酬月額の平均を30日で割った金額の3分の2に相当する金額になります。
埋葬料(まいそうりょう)
埋葬料は、従業員やその扶養者が亡くなった時に支給されます。
支給金額は5万円になります。
組合健保(組合管掌健康保険)について
組合健保は、大企業が自前で設立した組合が運営する健康保険です。
組合健保の場合、従業員と会社の保険料の負担割合は規約により定められるため、協会けんぽのように必ずしも折半になるとは限りません。
保険料以外は基本的に協会けんぽと同じ内容になりますが、大企業が自前で設立しているので、資金力がある場合には、協会けんぽより支給額が上乗せされている場合があります(付加給付といいます)。
組合健保(組合管掌健康保険)の保険内容の主なものは以下の通りになります。
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
従業員が療養のために、連続する3日間を含む4日以上仕事を休む場合に、最長で1年6か月間は傷病手当金を貰うことができます。
傷病手当金の金額は、標準報酬月額の平均を30日で割った金額の3分の2に相当する金額になります。
高額療養費(こうがくりょうようひ)
高額療養費とは、月にかかった医療費の自己負担額(全体の3割)が高額になった場合に、自己負担限度額(8万円強の人が多い)を超えた分の金額が、後から払い戻される制度です。
出産一時金
従業員が出産した場合には、出産育児一時金、従業員の家族が出産した場合には家族出産育児一時金が支給されます。
支給額は一人につき50万円となります。
出産手当金
出産日前42日と出産日後56日の間、休職した期間に応じて従業員に支給されるのが出産手当金です。
支給金額は、標準報酬月額の平均を30日で割った金額の3分の2に相当する金額になります。
埋葬料(まいそうりょう)
従業員やその扶養者が亡くなった時に支給されます。
支給金額は5万円になります。
国保(国民健康保険)について
国保とは自営業者や年金受給者が加入する健康保険で、運営主体は、市区町村・都道府県・国民健康保険組合になります。
保険料は、各市町村により異なり、家族の人数分の保険料を支払うことになります。
協会けんぽや組合健保などの企業型の健康保険との保険内容の違いは、休職した時の補償になる傷病手当金や出産手当金がない点です。
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、①75歳以上の人と②65歳から75歳未満の人で一定の障害状態になることについて認定を受けた人が加入できます。(75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。)
大きな特徴は、医療費の自己負担割合が3割ではなく、1割に減額され、保険料が年金から徴収されるということです。
現役並みの所得がある人の自己負担割合は3割になり減額されません。
また、2022年10月1日から一定以上の所得がある方の自己負担割合が2割になりました。条件に当てはまるかどうかは政府HP等でご確認下さい。

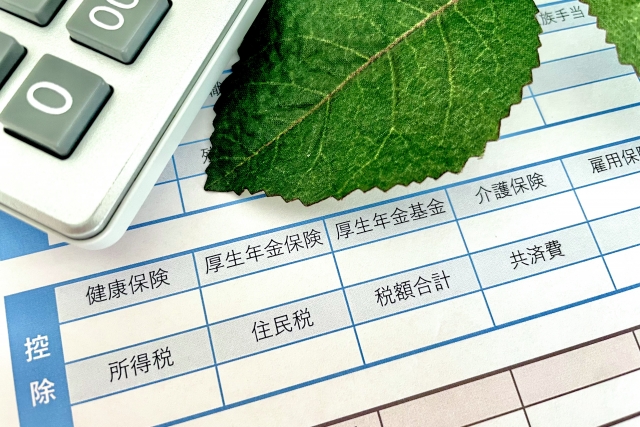
コメント